サステナビリティ
Sustainability
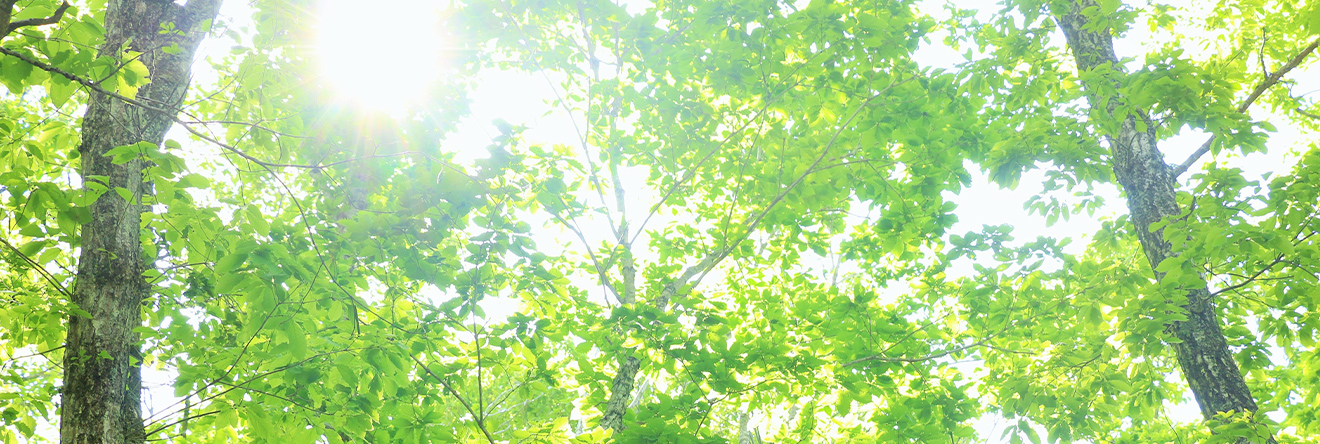

第3回ステークホルダー・ダイアログ(2025年9月)
【概 要】
第3回目となる2025年9月に実施したダイアログでは、外部有識者3名をお招きし、人的資本経営とDX推進をテーマに意見交換をいたしました。明治大学大学院の野田教授には、日本版ブルシット・ジョブ*や不寛容社会等をテーマとした基調講演を実施いただき、関西電力株式会社(以下、関西電力)の槇山氏とSGホールディングス株式会社(以下、SGホールディングス)の鳶川氏からは、各社における人材戦略や組織風土の醸成、DXの推進等に関する具体的な取り組み等についてご紹介をいただきました。
* 人類学者デヴィッド・グレーバーが提唱した概念。 働いている本人さえ必要がないと感じていて、世の中や社会に何の貢献もしない仕事のこと。
【出席者】
【外部有識者】
-

- 明治大学大学院 グローバル・ビジネス研究科
教授 - 野田 稔 氏 (ファシリテーター)
- 明治大学大学院 グローバル・ビジネス研究科
-

- 関西電力株式会社
執行役常務
ソリューション本部長代理
ガス事業本部長 - 槇山 実果 氏
- 関西電力株式会社
-

- SGホールディングス株式会社
人事部 担当部長 - 鳶川 尚子 氏
- SGホールディングス株式会社
【テスホールディングス株式会社】
- ●代表取締役社⾧ 山本 一樹
- ●専務取締役 髙崎 敏宏(テス・エンジニアリング株式会社 代表取締役社⾧兼務)
- ●取締役ESG・女性活躍推進担当兼人財戦略本部⾧ 吉田 麻友美(ESG推進委員会 委員⾧)
- ●管理本部 財務ユニット アセットマネジメントチーム長 伊東 紫
- ●人財戦略本部 人財開発チーム長 川島 愛那
- ●ESG 推進委員会 D&I(ダイバーシティー&インクルージョン)WG 松本 大樹*、今井 哲平*
- ●ESG 推進委員会 事務局 松本 善大*、松岡 映理*、水田 雛乃、谷川 晴希、浅田 愛梨
- ●その他オブザーバー*(監査等委員、内部監査室等)
- * オンライン参加
【外部有識者の方との意見交換】
経営層と従業員のコミュニケーションについて
テスホールディングス(以下、THD)吉田: 当社の課題として、経営層から管理職クラスへのコミュニケーションをより活発化させたいということが挙げられます。関西電力様は実際に組織風土改革の取り組みを実施されたとのことですが、取り組みによって何か変化を実感されたことはありますか?
関西電力 槇山氏: 着実に変化していると実感しています。一方で、モチベーションサーベイの結果を見ますと、経営層と従業員の思いに乖離があることが分かっており、当社としても課題と認識しています。
経営層は折に触れ、方針等をメールやポータルサイトを通じて発信しています。その上で経営層からミドルマネジメント層に方針や思いを共有し、彼らが自分の言葉で部下に伝えるという流れを基本としています。ただし、このプロセスでは、情報にフィルターがかかってしまい、経営層の思いや意図が正確に伝わらないことも少なからずあります。そのため、こうしたラインを通じた伝達に加え、経営層と従業員が直接対話する機会を設ける必要性を感じています。現在、こうした取り組みの具体的な方法について社内で議論を進めているところです。
明治大学大学院 野田氏: SGホールディングス様はいかがでしょうか?
SGホールディングス 鳶川氏: 当社でも同様の課題を抱えています。毎年実施しているエンゲージメント調査では、経営方針や会社の方向性に対する共感性の低さがエンゲージメント低下の主因として挙げられています。経営者は、部長やマネージャー層が従業員に方針をしっかり伝えることを期待していますが、現状ではその意向が十分に浸透していないと感じています。改善案として、関西電力様と同様に経営層と従業員が直接対話する場を設ける案が出ていますので、現在、実行に向けて計画中です。
明治大学大学院 野田氏: ある企業のグローバル展開において、価値観の伝達に苦労した経験があります。特に異文化間では、日本人の考え方を正確に伝えることが難しく、宗教の布教プロセスにヒントを得ました。特に注目したのは、キリスト教における価値観の伝達プロセスです。
かつてのキリスト教の布教は、非常に直接的なアプローチが中心でした。例えば、「これを信じれば、あなたの生活が豊かになる」といったメッセージが基本であり、文明の進んだキリスト教徒が未開の地の人々に「良い食事ができるから信じなさい」と説くような構図でした。しかし、現代の布教プロセスは大きく変化しています。現在では、「あなたの心の中にも神様がいます。あなたは今、何を大切にしていますか?」といった問いかけを通じて、相手の価値観に寄り添いながら伝える方法が主流です。例えば、「隣の家の方とはどのように接していますか?」と尋ねると、「仲良くするようにしています」といった答えが返ってきます。これはまさに聖書の「汝の隣人を愛せよ」に通じる考え方であり、すでに実践されている価値観であるにもかかわらず、本人がそれを自覚していないことも多いのです。このような気づきをもとに、「あなたの中にある聖書と共通する価値観を意識し、実行していきましょう。足りない部分があれば、そこを学んでいきましょう」というアプローチが有効であると感じました。つまり、「自分で考え実行するプロセス」がなければ、どんな価値観も本質的には伝わらないということです。この考え方をもとに、先述の企業のビジョン浸透にも応用し、現地で既に取り組みが始まっている事例を探し、「あなたの考えと我々のビジョンには共通点がありますね」と共感を生み出すことから始めました。さらに「あなたならどう実行しますか?」と問いかけることで、自ら考え、納得して動いてもらうプロセスを重視しました。もちろん、価値観のズレは避けられず、結果として“それぞれの国型”のビジョンになることもありましたが、それを否定せず、良い部分はグローバルビジョンに取り込むという柔軟な姿勢を取りました。この経験から得られた教訓は、ビジョンを上から一方的に浸透させるのではなく、従業員の思いや価値観とすり合わせながら、共に創り上げていくことの重要性です。人は、他者から指示されただけでは本気で取り組むことが難しいものですが、自分で考えた結果が会社のビジョンと一致していれば、納得感を持って取り組むことができます。つまり、「もう一度自分で考えさせるプロセス」なしに、ビジョンの浸透はあり得ないということです。ビジョンは、共創するものだと考えています。
THD 吉田: トップダウンで一方的に伝えれば良いというわけではなく、従業員が既に実行していることと会社の方針をすり合わせるプロセスが重要ということですね。
明治大学大学院 野田氏: その通りです。経営層がビジョンの浸透を図るためにコミュニケーション量を増やそうとするほど、従業員側の腰が引いけてしまうことがあります。一方的に言われれば言われるほど、心が閉ざされてしまう。むしろ従業員自身にビジョンを語ってもらうことで、より深い理解につながると考えます。
関西電力 槇山氏: 自分の考えを言葉にしてみると、整理できていると思っていたことが意外とそうでもないと気づくことがあります。対話することで新たな気づきが生まれ、自分ごととしてビジョンを捉えられるようになるのだと思います。 例えば、本店が策定したKPIを、一方的に第一線職場へ下ろすと「やらされ感」が生じることがありますが、第一線職場の意見を反映しながら、共に策定したKPIであれば、主体的に取り組む姿勢が生まれます。対話を重ねることは時間も労力もかかりますが、それが浸透への近道だと考えています。
明治大学大学院 野田氏: 以前、ある大手SIerで階層別研修を企画した際、ある課長から「全部できるわけがない」との声がありました。しかし、話を聞いてみると「一部はやってみたいと思っていた」とのことだったので、「興味のある部分だけで構いません」と伝えました。その後、「やってみたら面白かったので、他の施策にも取り組んでいます」と連絡をいただきました。やはり、自分ごと化して発信するプロセスが浸透の鍵だと感じています。
THD 吉田: 一方で、指示待ち型の従業員も一定数存在しており、そうした層にどう語らせるかが悩ましいところです。
明治大学大学院 野田氏: ある会社では、ビジョンの浸透において「全員へ一律に伝えることは難しい」と判断し、浸透のプロセスを設計することを考えました。段階的な浸透戦略です。この戦略の背景には「イノベーションの普及理論(ディフュージョンセオリー)」の考え方があります。この理論では市場を、イノベーター(新しいものに強い関心を持ち、誰よりも早く取り入れる層)、アーリーアダプター(新しい価値に敏感で、周囲への影響力も高い層)、アーリーマジョリティ(流行や実績を重視し、安心感が得られてから採用する層)等の層に分類しています。この企業では、イノベーターとアーリーアダプターには自然に浸透すると見込み、特にアーリーマジョリティ層の動かし方に注力していました。この層は慎重で、他者の評価や実績を重視する傾向があるため、「自分にとってどんな意味があるのか」を伝える、あるいは考えさせることが重要です。そのため、会社の職務階層的にビジョンを下ろすのではなく、親和性の高い人物(いわゆる“ノリの良い人”)を起点に伝えていくというアプローチが有効だとされました。こうした人を通じて、自然な形で周囲に広げていくことで、アーリーマジョリティ層にも浸透しやすくなるという考え方です。
THD 吉田: 階層的なアプローチではなく、階層の区別なく親和性の高い人物を起点にして浸透させていくという考え方は、これまで意識していなかった視点でした。非常に参考になりました。
DX推進への取り組みについて
THD 伊東: 弊社では、請求書処理の自動化を目的としたDX化に取り組みました。しかし、導入にあたっては、一部の方々から「現在の作業プロセスの方が早い」「効率が良い」といったご意見をいただきました。プロジェクト担当者も、こうした声に真摯に向き合いながら、導入の意義やメリットを丁寧に説明する必要がありました。
結果としてシステムの導入は進められましたが、導入後も「効果を実感しづらい」「逆に負荷が増えた」といった声が寄せられています。これらの反応は、業務の進め方が大きく変わることへの不安や戸惑いが背景にあると受け止めています。
今後もAIやシステムを活用した業務効率化の可能性は大きいと考えていますが、導入に際しては、現場の理解と納得を得ることが不可欠であり、各社の取り組み事例や助言があれば伺いたいです。
SGホールディングス 鳶川氏: 当社でも同様の課題がありました。人事関連の手続きをクラウド人事システムに移行する取り組みを進めましたが、ドライバーや現場の従業員はメールアドレスを持っていないケースも多く、紙文化が根強くのこっていました。2年ほど前から各事業会社に展開を進めていましたが、紙での手続きに慣れている人事担当者からは「紙の方が早い」「現場のドライバーはスマホを使いこなせない」といった意見もあり、トップの指示があっても現場では距離を置かれることが多くありました。そこで、関係する人事担当者を集め、週1回の定例会を継続的に実施し、「会社として取り組むべきことだ」という意識の醸成に努めました。この取り組みを半年ほど続けてようやく導入が進み始めたという状況です。変化を嫌う人ほど「自分の仕事は自分のやり方で」という意識が強いため、 会社全体で取り組む姿勢をどう浸透させるかが鍵だと感じています。
明治大学大学院 野田氏: 導入後の反応はいかがでしたか?
SGホールディングス 鳶川氏: 結果として業務の効率化が進み、導入して良かったと感じています。
社内アンケートでは「AIの普及で自分の仕事がなくなるのでは」という不安の声もありますが、逆に「AIを使いこなせる人材になりたい」と前向きに捉える従業員も増えているのではないかと思っています。
明治大学大学院 野田氏: 関西電力様はいかがでしょうか?
関西電力 槇山氏: 当社では、基本的に「やると決めたらやる」ことが多く、導入に対してNOとなることはほとんどありません。DXやAIは経営自らが率先して導入しよう!と進めていますが、DX化の実務で苦慮するのはむしろ私のような経営層のほうかもしれませんね。(笑)DX化に関して、現在は従業員からの要望も多く、DX化のプロジェクトは順番待ちになるほどです。私が所管するソリューション本部では、DX化の実務があまり得意でない第一線職場の高年齢層などの従業員においても、ノーコードのシステム開発研修を通じて「意外と容易に作れる、使える」ことを実感してもらうことで、やる気やスキル向上に繋がっています。DXは業務効率化や価値創出のツールだけではなく、リスキリングの機会としても有効だと感じています。
明治大学大学院 野田氏: DX化を推進するためには、まず「面白がる人」を増やし、やらない人を少数派にしていくしかないと思います。ある商社では、伝票や納期、支払い条件などが顧客ごとに異なる煩雑な業務を自動化しようとした際、「こんな複雑な業務が自動化できるわけがない」と反発がありました。しかし、実際に自動化が進むと「やればできる」と認識が変わり、一気に導入が進みました。それでも最後の最後まで1〜2割の従業員は動かず、残念ながら一定の覚悟を持って進める必要があると感じています。
DX推進体制について
THD 髙崎: 関西電力様では、DX推進のプランや仕組みは全社的に統括しているのでしょうか。それとも各本部が個別に推進しているかたちでしょうか。DX推進体制に教えてください。
関西電力 槇山氏: 当社には「IT戦略室」があり、全社的なポリシーやルール、セキュリティ方針の策定・管理を担っていますが、DX推進そのものは各事業部が主体となって進めています。2018年にアクセンチュア株式会社と共同で「K4 Digital株式会社」という会社を設立し、当社のDX化を推進してきました。現在、各事業部がAI活用を含めたDX化の方針を定め、それに対してK4 Digitalが支援を行うという形で進めています。
THD 髙崎: 各事業部門に専任のDX担当者がいるわけではないということでしょうか?
関西電力 槇山氏: 各事業部に専任のDX担当者を設置し、IT戦略室、K4Digitalと連携しつつ進めています。DX人材についてはキャリア採用を行うとともに、社内での育成にも力を入れています。全社的なDX研修に加え、各事業部での研修を通じて、素養を高めながら実務に落とし込む取り組みを進めています。
明治大学大学院 野田氏: 日常業務のデジタル化(デジタライゼーション)であれば、比較的スムーズに進むこともあります。周囲がDXに取り組んでいる様子を見ることで、自分もやってみようという意識が生まれるケースもあります。
THD 髙崎: 成功事例がでてくれば、それを模倣する動きも出てくると思います。当社では部門ごとに業務の特性も異なるため、それぞれでDXの検討進めていますが、全社的に統括した方が効率的ではないかと感じることもあります。
また、書類のデータベース化によるペーパーレス化を進めた際、現場からは「手間が増えるだけで管理部門が楽になるだけではないか」といった反発もありました。しかし、紙がなくなることでテレワークが可能になるなど、良い影響も出てきており、こうした好循環が広がれば、取り組みも加速するのではないかと考えています。
THD 吉田: 人は変化を嫌う傾向があるため、導入初期は反発が多くなるのは自然なことだと思います。重要なのは、一定期間を置いた後にどう評価されるかです。もし時間をかけても改善が見られない場合は、進め方に問題がある可能性もありますが、まずは一定期間、反発を受け止めながら継続することが必要だと考えています。
明治大学大学院 野田氏: ある情報関連会社では、情報システム部門の社員を「ダブルチェア」として各事業部にも配置しました。つまり、情報システム部門に所属しながら、事業部門のデジタル化支援も担うという体制です。月曜から木曜は各事業部門に常駐し、DX推進のサポートを行い、金曜日は本社の情報システム部門に戻って新技術の習得や、各部門での取り組みの情報共有を行っています。また、ある自動車メーカーでは、AIやPCに関心のある従業員を集め、Excelが使える程度のスキルでもデジタル人材として育成する取り組みを進めています。毎年1000名を超える規模でリスキリングを行い、採用が難しい分、自社内で人材を育てる方針を取っています。このように、事業部門内で興味がある人を見つけ、学ぶ機会を提供することでDX化が加速する可能性があるかもしれません。
中間管理職の業務負担について
THD 吉田: 本日の野田先生の基調講演でも中間管理職の負担増というお話がありました。この点、関西電力様ではどのような対策をとっていらっしゃいますか?
関西電力 槇山氏: やらなくてよい仕事を増やさないことや手戻りを増やさないことが重要だと考えています。指示を出す方は、より具体的で明確な指示を出す。指示を受けた方もその業務が必要な目的を理解するように心がけ、分からないことは早めに聞く。複数業務の指示をもらっている場合は、どちらを優先すべきか指示を仰ぐ。このように、指示を出す方と受ける方の両方での心掛けにより効率化が実現できると考えています。私自身も、私の部下に対しては、早い段階で口頭や箇条書きなどにより方向性を擦り合わせ、その上で資料作成に入っていただくよう心掛けています。
THD 吉田: その通りだと思います。指示を出す側も、他者への説明責任を果たす過程において思考もより一層明確になってくることもありますし、上司と言えども神ではなく、いち人間なので他者の意見を聞いてハッと気づくことや軌道修正することもあります。そのため、ある程度互いの間でキャッチボールがあった上でようやく「(指示を出す側として)本当にやって欲しいこと」と「(指示を受けた側として)本当にやるべきこと」が明確になるのだと思います。指示を出す側の上司の立場の方にはそういった良い意味での緊張感が必要で、指示を受ける側の立場の方には、自分の中で十分に消化しきれていない指示を前に思い悩むのではなく、早めに相手に尋ねることや考えを伝えるという勇気を持つことが必要ということですね。
360度評価の実施について
THD 吉田: 関西電力様では多面評価を実施されていると伺いました。当社でも360度評価の実施について検討しています。実施については、賛否両論あるため以下のような配慮が必要だと考えています。関西電力様での実施状況はいかがでしょうか?
・管理職といった限定的な範囲で行うこと
・評価に紐づけない、気づきや自己啓発を目的として行うこと
・評価を受け止める側と評価する側の両方に事前の教育を行うこと
関西電力 槇山氏: 当社では、多面評価については管理職を対象に実施しています。多面評価に携わった関係者を対象として実施したアンケートでは、被評価者の約8割が多面評価のメリットを感じており、フィードバックを通じて、業務運営や部下マネジメントの改善に役立てています。
THD 山本: 当社グループでも十分な配慮をした上で、実施できれば良いと考えています。先日、ある会社の社長から360度評価について話を伺いました。
その会社では、管理職に昇格させる際は必ず360度評価を実施し、同僚や部下からの賛同がなければ昇格できないというルールにしているそうです。上司からの評価がとても高い人財でも、同僚や部下からの評価が押し並べてとても悪いケースもあり、多面評価をやってよかったとのことでした。
当社グループのD&I研修について
THD 事務局: 人的資本経営に取り組む上での重要な要素のひとつとして、D&Iがあると思います。当社グループでも全役職員を対象に「D&I研修」を実施し、まずは社内におけるD&Iに対する理解促進や浸透に取り組んでいます。ただ、その中で「D&Iが大事なのは理解できたが、実際に何をすれば良いか分からない。」という意見もあります。このような状況を踏まえ、理解から次のステップへと進み、D&Iを自分ごととして捉えてもらうためには、どのような取り組みが必要なのでしょうか。
明治大学大学院 野田氏: 私であれば、例えば日本人にはあまり馴染みのない「人種」をテーマにしたケーススタディを実施すると思います。人種はそれぞれの国や場所ごとにマジョリティとマイノリティの構造があり、D&Iの要素である多様性と包摂性を考える上では有効な題材となります。
ここで重要なのは、D&Iを自分ごととして捉えてもらうために、現実に近すぎる題材をケーススタディに選ばないことです。例えば、実際の職場で起こり得ることを題材とすると、個人的な感情や経験が入り込み、フラットな視点で考えることが難しくなる場合があります。そのため、このような工夫もしながら「自分だったらどうするか?」という視点を持ち、主体的に考える機会を提供することが必要だと思います。
最後に
THD 山本: 当社グループは従業員数約400名~500名と中規模であるため、コミュニケーションの工夫次第で考え方を浸透させることは可能だと考えています。しかしながら、先日実施したエンゲージメント調査では、いわゆる「U字型」の傾向が見られました。年次が上がるにつれてエンゲージメントが低下し、一定の年次を超えると再び上昇するという結果です。昨年、中期経営計画を策定する際には、トップダウンの要素を含みつつも、従業員アンケートを参考にしたつもりでしたが、思うように浸透していないのが現状です。
従業員との距離が比較的近い規模であるからこそ、改めてコミュニケーションの取り方を見直す必要があると感じています。
現在は、毎週月曜日の朝8時から9時に、当社および子会社の業務執行役員10名による「朝会」を実施しており、課題の共有や意見交換を行っています。役員間のコミュニケーションは円滑になってきていますが、ミドル層への浸透にはまだ課題が残っています。一方で、若手社員とのコミュニケーションは比較的良好だと考えています。新入社員の最終面接には私、髙崎、吉田の3名が必ず出席しており、入社式や入社初期の研修でも関わる機会が多くあります。さらに、入社4年目までの社員とは「シャッフルランチ」と称して、私と髙崎が各拠点の若手社員とランチを共にする等、積極的に交流を図っています。
今後は、野田先生が仰っていたように、階層別ではなく、ビジョンに共感してくれる社員にどうアプローチするかも重要視していきたいと考えています。ただし、経営層からの働きかけが強すぎると、かえって従業員が口を閉ざしてしまう可能性もあるため、バランスを見ながら進めていきたいと思います。


